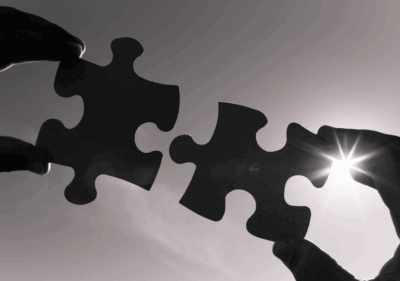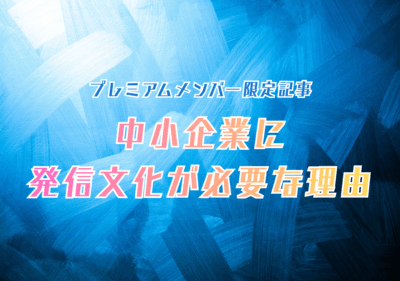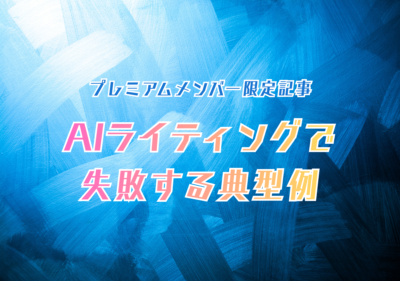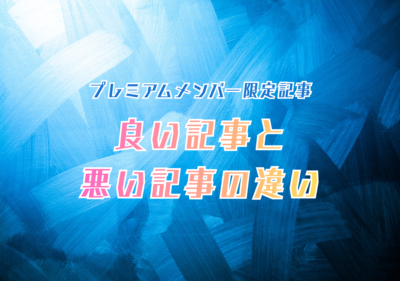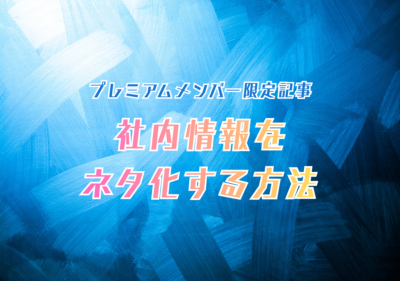「SEOってもう古いんじゃないか」と感じていませんか?
AIが質問に答えてくれる時代になり、SNSで情報が拡散される今、検索エンジン対策に力を入れる意味があるのか迷う方も多いでしょう。
確かに情報収集の方法は変化しています。しかしSEOは終わったのではなく、形を変えて進化しているのが実情です。むしろ企業にとっては、一時的なバズではなく「蓄積型発信とは何か?|続けることで成果を出す本質的な発信方法を徹底解説」で解説している蓄積型の発信として、今も重要な役割を果たしています。
この記事では、なぜSEOがオワコンと言われるのか、その背景を整理したうえで、企業の発信活動においてSEOが今も大切な理由を解説します。さらに、これから取り組むべきポイントもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
SEOがオワコンと言われる背景を整理する
「SEOはもうオワコンだ」という声を聞いたことはありませんか。情報の探し方は確かに変わってきていますが、それは本当にSEO対策が不要になったという意味なのでしょうか。
ここでは、なぜそう言われるようになったのか、背景を具体的に整理していきます。
AI検索の台頭で情報の探し方が変わっている
ChatGPTをはじめとするAI検索ツールの登場により、私たちの情報収集スタイルは大きく変化しています。質問を入力すれば、すぐに答えが返ってくる。わざわざ複数のサイトを比較する必要がなくなったと感じる人が増えているのです。
実際、Googleも検索結果画面でAIが要約した情報を表示する機能のテストを進めています。検索結果をクリックして各サイトを訪問する行動は減っていく可能性があります。
ただし、これはSEOの終わりを意味するわけではありません。情報の探し方が多様化しているという変化として捉えるべきでしょう。AIツールで得た情報をさらに深く知りたいとき、信頼できるサイトを求めて検索します。そこで選ばれるコンテンツを作ることが、これからのSEO戦略なのです。
SNSで情報を集める人が増えている現状
TwitterやInstagramで情報収集する人が増え、検索エンジン以外の入り口が広がっています。特に若い世代を中心に、SNSが主要な情報源になっている現実があります。
「とりあえずインスタで検索する」「Xで最新情報をチェックする」という行動は、もはや日常的なものになりました。動画コンテンツで学ぶスタイルも定着し、YouTubeで「やり方」を検索する人も増えています。
こうした変化は、確かに検索エンジンからの流入に影響を与えています。しかし、SNSで得た情報をさらに詳しく知りたいとき、多くの人はGoogle検索に戻ってきます。SNSとSEOは対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあるのです。
Googleアルゴリズムの変化で上位表示が難しくなっている
Googleの評価基準は年々厳しくなっており、以前のような方法では上位に表示されにくくなっています。キーワードを詰め込むだけの記事や、内容の薄いページは評価されなくなりました。
コアアップデートと呼ばれるアルゴリズムの大型更新により、順位が大きく変動するケースも増えています。一夜にして上位から圏外に落ちてしまった経験を持つ担当者も少なくありません。
ただし、この変化を悲観的に捉える必要はありません。Googleが目指しているのは、質の低い情報を排除し、本当に価値あるコンテンツを上位に表示することです。読者の悩みに向き合い、専門性の高い情報を提供する企業にとっては、むしろチャンスだと言えます。
ゼロクリック検索の増加で訪問数が減っている
検索結果の画面で答えが表示されて、サイトをクリックせずに解決してしまうケースが増えています。これをゼロクリック検索と呼びます。
Googleは検索結果ページに、質問への直接的な回答や地図情報、計算結果などを表示する機能を充実させてきました。その結果、ユーザーは検索結果ページから離れることなく、必要な情報を得られるようになったのです。
確かに、訪問数は減る傾向にあります。しかし、表面的な答えだけでなく、より深い理解や具体的な解決策を知りたい読者は存在し続けます。
だからこそ、簡単に要約できない専門的な内容や、実体験に基づく具体的な事例を盛り込むことが重要になります。「ここにしかない情報」を提供することで、訪問してもらえる価値を作り出せます。
今でもSEOが企業の発信活動で大切な理由
AI時代を迎え、情報収集の方法が変化する中でも、SEOは企業の発信活動において重要な役割を果たしています。ここでは、「蓄積型発信」という視点から、SEO対策が持つ本質的な価値について解説します。
発信した内容が長く資産として残り続ける
SEOで作成したコンテンツは、一度Web上に公開すれば消えることなく残り続けます。広告のように費用を払い続ける必要がないため、時間が経つほど企業の資産として価値が積み上がっていきます。
良質な記事は何年も検索結果に表示され、継続的に訪問者を呼び込んでくれます。例えば、2年前に作成した記事が今も毎月100人の訪問者を集めているとすれば、それは追加費用なしで働き続ける営業担当のようなものです。
この「蓄積型の発信」は、特に中小企業にとって大きな意味を持ちます。「中小企業が蓄積型発信に取り組むべき理由|場当たり発信を卒業する成長戦略の新常識」で詳しく解説していますが、限られた予算の中で、持続的に効果を生む手段として、SEO対策は今も十分な価値があるのです。
能動的に情報を探している人に届けられる
検索エンジンを使う人は、具体的な悩みや課題を抱えて能動的に答えを求めています。「資産になる発信と一過性の発信の違い|効果が続く発信で成果を積み上げる方法」で解説しているように、SNSで流れてくる情報を眺めるのとは違い、自ら行動して解決策を探している状態です。
このような読者は、記事を深く読み込み、内容に納得すれば問い合わせや資料請求といった行動につながりやすい特徴があります。信頼関係を築く入り口として、検索経由の接点は今も非常に有効です。
特にBtoB分野や専門性の高いサービスでは、じっくり比較検討したい人が検索エンジンを利用します。こうした意欲の高い読者に、的確な情報を届けられることがSEOの強みなのです。
広告と違い費用をかけずに続けられる
広告は予算が尽きれば効果も止まってしまいますが、SEOで作ったコンテンツは追加費用なしで働き続けます。一度作成した記事が、何ヶ月も何年も訪問者を呼び込んでくれるのです。
もちろん、記事作成には時間と労力がかかります。しかし、いったん公開すれば、その後は大きなコストをかけずに成果を生み出し続けます。
この仕組みは、特に中小企業にとって大きな価値があります。毎月の広告費を捻出するのが難しい状況でも、コツコツと記事を積み重ねることで、安定した集客の基盤を作ることができるのです。
専門性や信頼性を積み上げられる仕組み
実際に記事を書く際には、まず「この記事を読む人はどんなことで困っているのか」を考えてみましょう。そして、その悩みに対して具体的な解決策を示すことを心がけてください。専門用語を避けて分かりやすく書き、「明日から実践できる」レベルの具体例を入れると、価値のあるコンテンツになります。
例えば、ある課題について検索したときに、同じ会社の記事が何度も目に入るようになると、「この会社は詳しそうだ」と感じます。専門知識を持つ企業として認知され、選ばれる理由になっていきます。
この信頼の蓄積は、広告では得られない価値です。「なぜ発信が企業価値を高めるのか?|中堅企業が知るべき売上向上メカニズムの全解明」で詳しく解説していますが、SEOを通じた発信活動は、企業のブランド構築にも大きく貢献します。今すぐ始めることで、将来の信頼獲得につながる第一歩を踏み出せるでしょう。
これから取り組むべきSEOのポイント
AIが質問に答える時代になり、情報収集の手段が多様化する中で、これからのSEO対策はどう進めればよいのでしょうか。
ここでは、今後のSEOで大切になる考え方を具体的に紹介します。読者の役に立つことを第一に考える姿勢が、結果的に評価される仕組みであることをお伝えします。
読者の悩みに真摯に答える記事を作る
検索エンジンで上位を狙うテクニックよりも、本当に読者の困りごとを解決する内容を書くことが大切です。
キーワードとは、検索エンジンで情報を探すときに入力する言葉のことです。例えば「肩こり 解消法」のように、悩みを解決するために使われます。かつては、このキーワードを記事の中に何度も詰め込めば上位表示されると言われていました。しかし現在のGoogleは、キーワードの数ではなく「読者の悩みにきちんと答えているか」を重視するようになっています。
実際に記事を書く際には、まず「中小企業のターゲット設定とペルソナの作り方|限られた予算で新規開拓を成功させる実践法」を参考に、「この記事を読む人はどんなことで困っているのか」を考えてみましょう。そして、その悩みに対して具体的な解決策を示すことを心がけてください。専門用語を避けて分かりやすく書き、「明日から実践できる」レベルの具体例を入れると、価値のあるコンテンツになります。
こうした姿勢で作った記事は、結果的にSEOの評価も高まっていきます。読者の役に立つことを第一に考える。これが、これからのSEO対策の基本です。
-
キーワード重視
検索語句の詰め込み -
テクニック中心
機械的な最適化 -
短期的成果
一時的な順位上昇 -
検索エンジン向け
アルゴリズム対策 -
量を優先
記事数の追求
-
読者重視
悩み解決を優先 -
価値提供
実用的な情報発信 -
長期的資産
持続的な価値創造 -
ユーザー向け
体験価値の向上 -
質を優先
深い専門性追求
AI検索にも対応できるコンテンツ作りを意識する
ChatGPTなどの生成AIとは、質問を入力すると自動的に文章を作成してくれるツールのことです。例えば「肩こりの解消法を教えて」と聞くと、すぐに答えを返してくれます。このAIが答えを作るときには、ウェブ上の様々な記事から情報を引用しています。
つまり、AIが答えを引用しやすいように、情報を整理して分かりやすく構成する工夫が必要になってきました。見出しを適切に使い、結論を明確に書くなど、AIにも人にも理解されやすい書き方を意識しましょう。
具体的には、記事の冒頭で「この記事では〇〇について解説します」と明示する。各セクションで伝えたいポイントを一文でまとめる。箇条書きや表を使って情報を整理する。こうした工夫によって、AIが情報を正確に読み取りやすくなります。
AI検索への対応は、決して難しいことではありません。読者にとって分かりやすい記事を作れば、自然とAIにも理解されやすいコンテンツになっていきます。
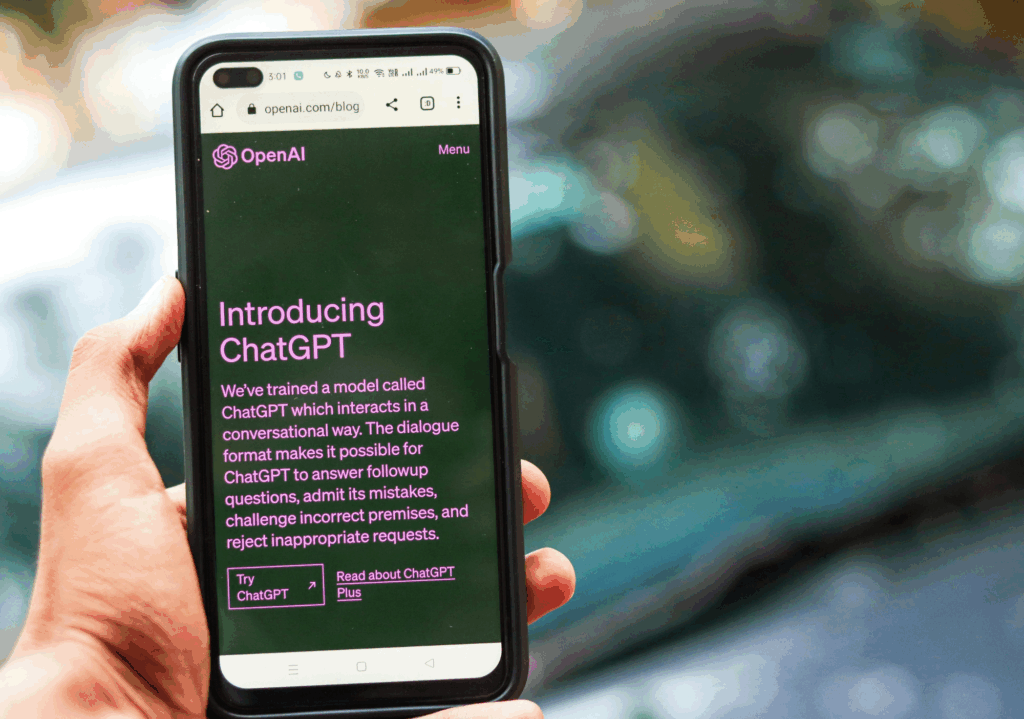
SEO単体ではなく他の発信手段と組み合わせる
SEO対策だけに頼るのではなく、SNSやメール配信など複数の方法を組み合わせる重要性が高まっています。それぞれの特性を活かして補い合うことで、安定した発信活動ができるようになります。
例えば、SEOで作成した記事をSNSで紹介すれば、検索エンジン経由以外の読者にも届けられます。また、記事の内容をメールマガジンで配信することで、既存の顧客との関係も深められます。このように、一つのコンテンツを複数のチャネルで活用することで、発信の効率が大きく向上します。
SNSとは、InstagramやX(旧Twitter)のように、人と人がつながって情報を共有するサービスのことです。投稿がすぐに拡散される特徴があり、タイムリーな情報発信に適しています。一方、SEOで作った記事は、長期間にわたって検索結果に表示され続ける強みがあります。
短期的な認知拡大はSNS、持続的な信頼構築はSEO、既存顧客との関係維持はメール配信といった形で役割を分けて考えると良いでしょう。複数の手段を組み合わせることで、一つの方法に依存するリスクも減らせます。
焦らず長期的な視点で続けていく
すぐに結果が出なくても諦めず、コツコツと積み重ねる姿勢が大切です。SEO対策は、広告のように予算を投入すればすぐに効果が出るものではありません。
良質な記事を作り、それが検索エンジンに評価されるまでには、通常3ヶ月から半年ほどの時間がかかります。記事の数が増え、サイト全体の専門性が認められるようになると、さらに評価が高まっていきます。この蓄積型の発信は時間がかかりますが、続けることで確実に企業の資産になっていきます。
月に2本でも3本でも構いません。無理のないペースで記事を公開し続けることが重要です。一時的に頑張って大量の記事を作るよりも、継続できる体制を整える方が、成果につながります。
今日始めた発信活動は、半年後、1年後の集客を支える基盤となります。焦らず、読者のために価値ある情報を届け続けましょう。その積み重ねが、やがて信頼という形で返ってきます。
まとめ:SEOは終わっていない、形を変えて進化している
SEOがオワコンと言われる背景には、AI検索の台頭やSNSへの情報収集シフトなど、確かな変化があります。しかし、それはSEOの終わりではなく、情報収集手段の多様化を意味しています。
企業の発信活動において、SEOは今も重要な役割を果たしています。一度作成したコンテンツが企業の資産として長く残り続け、能動的に情報を探している人に届けられる。広告と違い継続的な費用がかからず、専門性や信頼性を積み上げられる。これらは、蓄積型発信ならではの価値です。
これからのSEOで大切なのは、読者の悩みに真摯に答えること、AI検索にも対応できるコンテンツ作り、他の発信手段との組み合わせ、そして長期的な視点で続けていく姿勢です。
すぐに結果が出なくても諦めず、コツコツと価値ある情報を発信し続けましょう。その積み重ねが、やがて企業の信頼という形で返ってきます。今日から始める一歩が、未来の集客基盤を作ります。
SEO対策をさらに深く理解するための関連記事
「コンテンツマーケティングとSEOの違いをわかりやすく解説」
SEOとコンテンツマーケティングの関係性を理解することで、より効果的な発信戦略を構築できます。両者の違いと連携方法を詳しく解説しています。
「初心者でもできる!コンテンツマーケティングの始め方と継続成功のコツ」
SEO記事制作が初めての方向けに、最初の一歩から継続のコツまで、実践的な手順を丁寧に解説しています。
「BtoB企業が成果を出すコンテンツマーケティングの始め方」
BtoB企業特有の課題を踏まえたSEO戦略とコンテンツマーケティングの実践方法を紹介しています。
「コンテンツマーケティングの種類と選び方|予算と人手に合わせた始め方」
自社のリソースに合わせて最適なコンテンツマーケティング手法を選ぶための実践ガイドです。