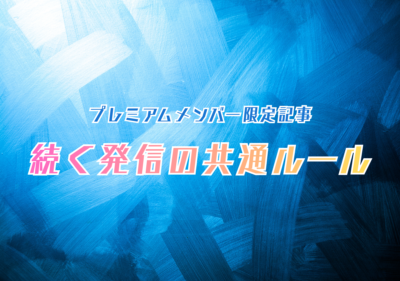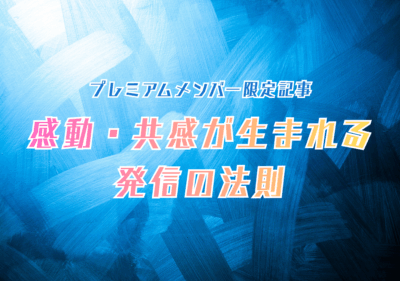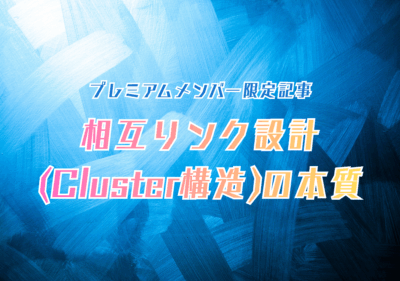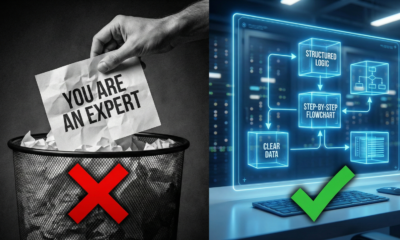コンテンツマーケティングに取り組みたいと考えているものの、記事や動画、ホワイトペーパーなど種類が多すぎて、どれから始めれば良いのか迷っていませんか。予算も人手も限られている中で、すべてに同時に取り組むことは現実的ではありません。
この記事では、コンテンツマーケティングの主要な7つの種類を、制作難易度や必要なコストとともに解説します。さらに、自社の状況に合わせた選び方や、少ない労力で複数のコンテンツを展開する実践的なノウハウもご紹介します。
読み終えた後には、自社に最適な種類が明確になり、明日から具体的に動き出せるようになります。短期的な注目ではなく、「資産になる発信と一過性の発信の違い|効果が続く発信で成果を積み上げる方法」で解説しているような、長期的に価値を積み重ねる発信を目指しましょう。
自社に合った種類を見つける選択基準
コンテンツマーケティングの種類を選ぶ際には、闇雲に始めるのではなく、まず自社の現状を冷静に見つめることが大切です。予算や人手、ターゲットの行動習慣といった要素を整理することで、無理なく続けられる方法が見えてきます。
どのような基準で選択すればよいかが明確になれば、効果的な発信の第一歩を踏み出せるようになります。
まず確認したい4つのチェックポイント
「初心者でもできる!コンテンツマーケティングの始め方と継続成功のコツ」でも触れていますが、コンテンツマーケティングを始める前に、以下の4つの観点から確認していきましょう。
1. 確保できる予算はどのくらいか
月にどれだけの金額を投資できるかによって、取り組める種類が変わってきます。月額10万円未満であれば、記事コンテンツやSNS投稿から始めるのが現実的です。外部への制作依頼ではなく、社内で書ける範囲から始めることで、費用を抑えながらノウハウを蓄積できます。
2. 社内の制作体制はどうなっているか
専任の担当者がいるか、それとも兼任なのかで戦略は大きく変わります。専任担当者がいない場合は、内製しやすい種類を優先する必要があるでしょう。例えば、いきなり動画制作に挑戦するよりも、文章で伝える記事コンテンツやSNS投稿の方が取り組みやすくなります。
制作に慣れてきたら、徐々に難易度の高い種類に挑戦していく段階的なアプローチが成功のカギです。
3. ターゲット顧客はどのように情報と接しているか
顧客がどの媒体で情報を得ているかを把握することも重要です。BtoB企業の場合、検索エンジンやメールマガジンが効果的な場合が多くあります。一方、BtoC企業であればSNSや動画の方が顧客の目に触れやすいかもしれません。
自社の顧客が普段どのような方法で情報収集しているのか、営業担当者にヒアリングしたり、アンケートを実施したりして確認しましょう。
4. 成果が出るまでどのくらい待てるか
短期間で成果を求めるのか、それとも長期的な資産を作りたいのかによっても選択は変わります。すぐに商談につなげたい場合は、ウェビナーやホワイトペーパーが向いています。
一方で、継続的に価値を積み重ねる発信を目指すなら、記事コンテンツが適しています。「コンテンツマーケティングとSEOの違いをわかりやすく解説」で詳しく解説していますが、SEOとは検索エンジン最適化のことで、時間はかかりますが、一度上位表示されれば長期的に安定した流入が見込めます。
顧客の購買プロセスから考える種類の選び方
顧客は商品やサービスを購入するまでに、いくつかの段階を経ていきます。この購買プロセスを理解することで、どの種類のコンテンツが効果的かが見えてきます。
次の図で、各段階に適したコンテンツの種類を確認してみましょう。
認知段階:企業やサービスを知ってもらう
まだ顧客は自社のことを知りません。SNS投稿や検索エンジンからの流入を狙った記事コンテンツが効果的です。例えば、業界のトレンドや課題について解説する記事を公開すれば、悩みを抱えた方が検索を通じて自社サイトを訪れてくれます。
興味関心段階:より詳しい情報を求める
認知した後、顧客は自社のサービスについてもっと知りたいと考えます。動画コンテンツやメールマガジンが有効です。動画であれば視覚的に情報を伝えられるため、記事よりも理解が深まりやすくなります。
メールマガジンを通じて定期的に情報を届けることで、継続的な接点を維持できます。
比較検討段階:他社と比べて判断する
顧客が具体的に検討を始めたら、事例コンテンツやホワイトペーパーの出番です。実際の導入事例を紹介することで、自社のサービスがどのような成果を生み出せるのかを具体的にイメージしてもらえます。
ホワイトペーパーでは専門的な情報を提供し、ダウンロードと引き換えに連絡先を獲得することで、営業活動につなげられます。
購入段階:最終的な決断を後押しする
最後の一押しとして、ウェビナーが効果的です。リアルタイムで質問に答えることで、顧客の不安を解消し、信頼関係を築けます。また、参加者は購買意欲が高い傾向にあるため、商談につながりやすいのも特徴です。
このように、顧客がどの段階にいるのかを考えることで、適切な種類を選択できます。
予算別に始められるコンテンツの組み合わせ
予算の制約がある中で効果を出すには、複数の種類を組み合わせて展開することが重要です。ここでは、予算別に現実的な組み合わせをご紹介します。
以下の表で、予算帯ごとに取り組める内容を整理しましたので参考にしてください。
| 項目 | 月額10万円以下 | 月額10〜30万円 | 月額30万円以上 |
|---|---|---|---|
| 推奨コンテンツ |
|
|
|
| 月間制作本数の目安 |
|
|
|
| 外注費用の目安 |
|
|
|
| 特徴 |
基礎的なコンテンツ制作中心。内製との組み合わせで効率化を図り、少ない予算でも継続的な発信が可能。
|
複数チャネルでの展開が可能。認知から興味関心まで幅広くカバーし、バランスの良い施策展開ができる。
|
包括的な施策展開で成果重視の本格運用。比較検討段階まで対応し、高い成約率を目指せる。
|
SNS投稿:20〜30本
簡易デザイン込み
動画:2〜3本
メルマガ:週1回配信
動画:1本5〜10万円
メルマガ配信:月1万円
動画:4〜5本
ウェビナー:月1回
事例:四半期1本
動画:1本10〜15万円
ウェビナー:1回10万円
事例取材:1本15万円
※ 初期段階では小規模から始め、成果を見ながら段階的に予算を増やすことをお勧めします。
※ 内製化できる部分は社内で対応することで、より効率的な運用が可能になります。
月額10万円以下:初心者向けの組み合わせ
限られた予算で始めるなら、記事コンテンツとSNS投稿から取り組みましょう。「中小企業が蓄積型発信に取り組むべき理由|場当たり発信を卒業する成長戦略の新常識」でも解説しているように、少ない予算でも継続的な取り組みで大きな成果を生み出せます。記事を月に4〜8本程度作成し、その内容をSNSで要約して投稿します。
一つの記事から複数のSNS投稿を作ることで、制作の負担を減らしながら多くの接点を作れます。外部ライターに依頼する場合、1記事あたり1万円〜2万円が相場です。社内で書ければ、さらに費用を抑えられます。
この予算内でも、記事の一部を深掘りしてホワイトペーパーにすることは可能です。既存の記事をまとめて再構成するだけなら、追加コストをかけずに新しいコンテンツを生み出せます。
月額10〜30万円:バランス重視の組み合わせ
この予算があれば、記事コンテンツに加えて動画やメールマガジンにも挑戦できます。記事を月に8〜12本作成し、そのうち2〜3本を動画化します。動画は簡易的なものであれば5万円〜15万円程度で制作できるため、予算に応じて調整が可能です。
メールマガジンは配信ツールを使えば月額数千円から始められ、記事の更新情報や業界ニュースを定期的に届けることで、顧客との接点を維持できます。
このように、複数の種類を組み合わせることで、認知から興味関心までの段階をカバーできます。
月額30万円以上:成果重視の組み合わせ
十分な予算がある場合は、ウェビナーや事例コンテンツにも取り組みましょう。記事コンテンツと動画に加えて、月に1回のウェビナーを開催します。ウェビナーの内容を記事化すれば、参加できなかった方にも情報を届けられます。
事例コンテンツは取材や撮影が必要なため制作に時間がかかりますが、比較検討段階の顧客に強い説得力を持ちます。四半期に1本のペースで作成すれば、無理なく継続できるでしょう。
どの予算帯であっても、一時的なバズではなく、長期的に価値を積み重ねる発信を意識することが大切です。まずは自社の状況に合わせて小さく始め、成果を見ながら徐々に種類を増やしていきましょう。
主要7種類の特徴と始めやすさを比較
コンテンツマーケティングには様々な種類があり、それぞれ制作難易度や必要なコストが異なります。ここでは、記事コンテンツ、SNS投稿、動画、ホワイトペーパー、メールマガジン、ウェビナー、事例という7つの主要な種類をご紹介します。
始めやすさや制作の難しさを明確にすることで、自社に合った種類を選びやすくなるでしょう。
記事コンテンツ|最も取り組みやすい基本の形
記事コンテンツは、コンテンツマーケティングの中で最も始めやすい種類です。専門的な機材やツールが不要で、WordPressなどのブログツールがあれば今日から発信を始められます。 一般的なSEO記事(3,000文字程度)であれば、ライティング経験者で1記事あたり3〜5時間程度が目安です。外注する場合のコストは1本5,000円から3万円程度と手頃です。
認知段階の顧客に特に効果的で、検索エンジンから継続的に流入を獲得できます。SEOとは検索エンジン最適化のことで、Googleなどで検索した時に自社サイトが上位に表示されるよう工夫することです。 一度公開すれば長期的に価値を生み続け、企業の資産として積み重なっていくのが大きな特徴といえます。
自社の状況に合わせて、無理のないペースで記事を作成し、顧客の悩みに寄り添った情報提供を続けましょう。

SNS投稿|日常的な発信で関係を築く
SNS投稿は、顧客との距離を縮める手段として有効です。Facebook、Instagram、Twitter、TikTokなど、ターゲット顧客の属性に合わせてプラットフォームを選べます。 記事コンテンツで作成した内容を要約して投稿すれば、より多くの人に情報を届けられるでしょう。
定期的な発信を続けるには相応の人手がかかります。拡散力が高く認知拡大には効果的ですが、一時的なバズではなく、地道な関係構築を重視する姿勢が大切です。
コメントへの返信や日々のコミュニケーションを通じて、顧客との信頼関係を築いていきましょう。
動画コンテンツ|視覚的に伝える効果的な手段
動画コンテンツは、視覚的に情報を伝えやすく、興味関心段階の顧客に効果的です。複雑なサービスの仕組みや製品の使い方を、文字よりも分かりやすく説明できます。 YouTubeなどのプラットフォームを活用すれば、配信コストを抑えながら多くの人に届けられるでしょう。
撮影機材の準備、編集作業、台本作成など、記事コンテンツに比べて工数が多くなります。編集のみの簡易的なものでも5万円程度から、企画・撮影・編集を含む本格的な制作なら30万円から100万円程度の費用が必要です。
記事コンテンツやSNS投稿である程度の経験を積んでから、動画制作に挑戦するのが現実的といえます。

ホワイトペーパー|比較検討段階で役立つ資料
ホワイトペーパーは、比較検討段階の顧客に役立つ専門的な資料です。業界の課題や解決策を詳しくまとめた内容で、ダウンロードと引き換えに顧客の連絡先を獲得できます。 リードとは見込み顧客のことで、将来的に購入につながる可能性のある顧客を指します。
既に作成した記事コンテンツをベースに作成できるのが利点です。複数の関連記事をまとめて再構成し、より詳しい解説を加えることで、ダウンロード資料として提供できます。 一方で、内容の専門性を保つため、定期的な更新が必要になります。
信頼を得やすい手法として、多くのBtoB企業が活用しているコンテンツ種類です。
メールマガジン|継続的に情報を届ける仕組み
メールマガジンは、興味を持った顧客に継続的に情報を届ける手段として有効です。記事コンテンツやホワイトペーパーの更新情報、ウェビナーの開催案内など、他のコンテンツと組み合わせて活用しやすい種類といえます。 配信ツールを使えば、月額数千円から始められるのも魅力です。
効果を実感するには配信リストの構築に時間がかかります。ウェブサイトでの登録フォーム設置、SNSでの呼びかけ、セミナー参加者への案内など、地道な取り組みが必要です。
開封率やクリック率を測定しながら、顧客のニーズに合わせた情報提供を続けていきましょう。
ウェビナー|双方向のやり取りで理解を深める
ウェビナーは、オンラインセミナーのことで、購入段階の顧客との双方向のやり取りを可能にします。リアルタイムで質問に答えられるため、顧客の不安や疑問を直接解消でき、信頼関係を深めやすい種類です。 比較検討段階から購入段階にかけて、特に効果を発揮するでしょう。
テーマ設定、資料作成、集客、当日の運営、フォローアップなど、企画から運営まで複数の工程が必要です。しかし、録画した内容を記事化したり、動画コンテンツに展開したりすれば、一つの企画から複数の成果を生み出せます。
まずは小規模なウェビナーから始めて、運営ノウハウを蓄積していきましょう。

事例コンテンツ|実績を通じて信頼を得る
事例コンテンツは、実際の導入事例や成功事例を紹介する種類です。比較検討段階の顧客に具体的なイメージを与え、「この会社なら安心できる」という信頼を得やすくなります。 他社の成功例を示すことで、自社サービスの効果を客観的に証明できるのが強みです。
課題、解決策、成果という流れで事例をまとめることで、読者は自社の状況に置き換えて考えやすくなります。インタビューや取材が必要なため制作には時間がかかり、定期的な更新も求められます。
顧客の協力を得ながら、説得力のある事例を積み重ねていくことが、長期的な信頼の蓄積につながるでしょう。
少ない労力で効果を高める実践ノウハウ
限られた予算や人手でも、工夫次第で効果的な発信は可能です。一つのコンテンツを複数の形式に展開する、無理のないペースで計画を立てる、段階的に取り組みを広げるという3つのアプローチを実践すれば、少ないリソースでも成果を積み重ねられます。
ここでは、明日から実行できる具体的な方法をご紹介します。
一つの内容を複数の形式に展開する方法
同じテーマを異なる形式で発信すれば、効率的に多くの顧客へ情報を届けられます。
ウェビナーの内容を記事として公開すれば、参加できなかった方にも情報が届き、検索エンジンからの流入も期待できます。関連する記事をまとめてホワイトペーパーに再構成すれば、ダウンロード資料としてリード獲得にも活用可能です。動画の文字起こしを記事にする展開も有効で、視聴時間がない方やテキストで確認したい方にも対応できます。
以下の表で、具体的な展開パターンを確認しましょう。
| 元のコンテンツ | 展開先の形式 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| ウェビナー | 記事ブログ投稿 |
SEO効果
アーカイブ化
|
| ウェビナー | 動画YouTube |
リーチ拡大
視聴機会増加
|
| 記事 | ホワイトペーパーPDF |
リード獲得
専門性アピール
|
| 記事 | SNS投稿要約版 |
認知拡大
エンゲージメント向上
|
| 動画 | 記事文字起こし |
情報の再利用
アクセシビリティ向上
|
| 動画 | ポッドキャスト音声版 |
ながら聴き対応
新規層開拓
|
| ホワイトペーパー | ウェビナー解説セミナー |
対話型コンテンツ化
理解度向上
|
| ホワイトペーパー | インフォグラフィックビジュアル化 |
SNS拡散力向上
理解促進
|
| インフォグラフィック | 動画アニメーション |
注目度向上
ストーリー化
|
| ポッドキャスト | 記事要約記事 |
SEO効果
読み返し可能
|
無理のないペースで継続する計画の立て方
信頼を築くには継続が不可欠です。そのため、自社の体制に合わせた現実的なペース設定が重要になります。
初めて取り組む場合、記事を月4〜6本程度から始めると良いでしょう。これにSNS投稿を組み合わせることで、多様な接点を作れます。記事制作には、簡易的なものでも1本あたり数時間、SEO対策を意識すると10時間以上かかることもあります。曜日ごとにテーマを決めておけば、制作がスムーズになります。月曜日は業界トレンド、水曜日はノウハウ解説、金曜日は事例紹介といったルールを作れば、ネタ探しの時間も削減できます。
3ヶ月後に見直して広げる段階的なアプローチ
最初から全てに取り組むのではなく、小さく始めて徐々に広げる方が成功につながります。
記事とSNSから始めて、3ヶ月後にアクセス状況や反応を確認しましょう。読まれている記事のテーマや反響の大きい投稿を分析し、その内容を動画やホワイトペーパーに展開します。特定のノウハウ記事が人気であれば、詳しく解説する動画を制作すると効果的です。短期的な注目ではなく、長期的に価値を積み重ねる発信を意識することで、企業の資産となるコンテンツが蓄積されていきます。
今日から記事1本の制作計画を立ててみましょう。
まとめ
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。コンテンツマーケティングの種類選びで迷っていた皆様に、自社に最適な選択肢を見つけていただけるヒントをお届けできていれば幸いです。ここで改めて、記事の重要なポイントを振り返ってみましょう。
- 予算や人手、ターゲット顧客の情報接触習慣を整理することで、自社に合ったコンテンツの種類を無理なく選べる
- 記事コンテンツから始めて段階的に動画やホワイトペーパーに展開することで、限られたリソースでも効果的な発信が可能になる
- 一つのコンテンツを複数の形式に展開する工夫により、少ない労力で多様な接点を作り出せる
コンテンツマーケティングは、一時的な注目を集めることではなく、長期的に信頼と価値を積み重ねていく取り組みです。すべての種類に同時に取り組む必要はありません。まずは自社の状況に合わせて記事コンテンツやSNS投稿から小さく始め、成果を確認しながら徐々に広げていくことが成功への近道です。今日から最初の一歩として、ターゲット顧客の悩みに寄り添った記事を一本作成してみてはいかがでしょうか。継続的な発信を通じて、御社ならではの価値を届けていきましょう。
この記事を読んだ方におすすめの関連記事
- 「コンテンツマーケティング成功の法則|月10万円以下で始める中小企業の実践方法と失敗回避策【事例あり】」 具体的な成功事例と失敗回避策を学べる実践ガイド
- 「初心者でもできる!コンテンツマーケティングの始め方と継続成功のコツ」 初めてコンテンツマーケティングに取り組む方向けの完全ガイド
- 「BtoB企業が成果を出すコンテンツマーケティングの始め方」 BtoB企業特有の課題と解決策を詳しく解説
- 「蓄積型発信とは何か?|続けることで成果を出す本質的な発信方法を徹底解説」 コンテンツマーケティングの根幹となる「蓄積型発信」の考え方を理解