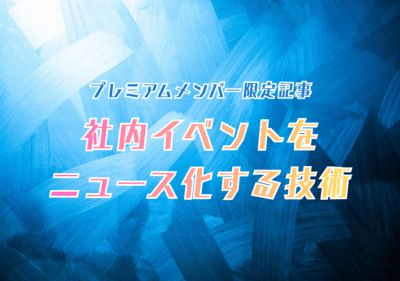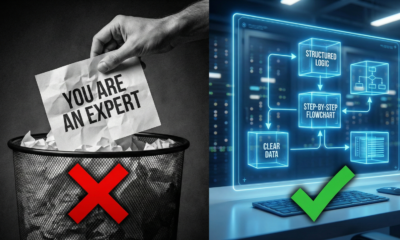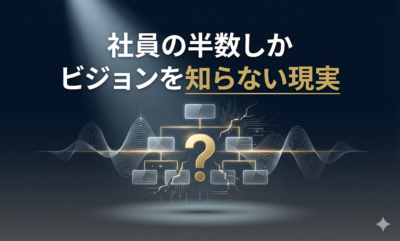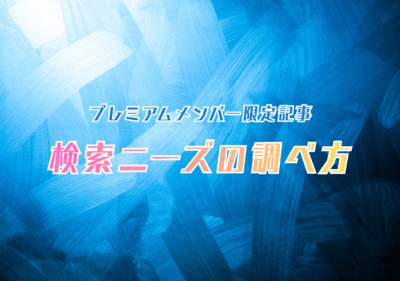「コンテンツマーケティングを始めたいけれど、うちのような中小企業には無理だろう」そんな風に感じていませんか?
実際に、多くの企業がコンテンツマーケティングに挑戦しながらも、期待した成果を得られずに悩んでいます。しかし、成功している企業には共通したポイントがあるのです。それは、豊富な予算や大きなチームではなく、適切な戦略と継続的な取り組みです。
本記事では、予算や人員に制約がある中でも成果を上げた15の事例を通じて、コンテンツマーケティング成功の法則をお伝えします。月10万円以下で始められる実践方法から、よくある失敗パターンとその回避方法まで、明日から実行できる具体的な手順をご紹介いたします。これらの事例を参考にすることで、あなたの会社でも効果的な発信活動を実現できるでしょう。
なぜ多くの企業が期待した成果を得られないのか|成功と失敗を分ける3つの違い
コンテンツマーケティングに取り組む企業は年々増加していますが、実際に期待した成果を得られている企業は決して多くありません。多くの担当者が「記事を書いているのに問い合わせが増えない」「SNSで発信しているのに売上につながらない」といった悩みを抱えています。
しかし、成功している企業と失敗している企業には明確な違いがあります。それは予算の大きさや人員の多さではなく、発信に対する考え方と実践方法にあるのです。ここでは、多くの企業が陥る3つの失敗パターンと、成功企業が実践している重要なポイントを詳しく解説いたします。
この違いを理解することで、あなたの会社でも効果的な発信活動を実現し、継続的に価値を積み重ねる「蓄積型発信」による成果を手に入れることができるでしょう。
自社の商品に興味がない人ばかり集めてしまう失敗パターン
多くの企業が陥る最初の失敗は、発信内容と自社の商品やサービスがつながっていないことです。例えば、会計ソフトを販売している会社が、お料理のレシピや健康に関する記事ばかりを投稿しているケースがあります。
このような発信を続けると、確かにアクセス数は増えるかもしれませんが、集まる読者は自社の商品に全く関心がない人ばかりになってしまいます。結果として、どれだけ多くの人に見てもらっても、問い合わせや売上にはつながりません。
売上につながる
売上につながらない
この失敗が起きる理由は、「多くの人に見てもらいたい」という気持ちが先行してしまうからです。しかし重要なのは、少なくても自社の商品やサービスに興味を持つ可能性がある人に、価値ある情報を届けることなのです。
発信することが目的になり売上につながらない問題
2つ目の失敗パターンは、記事を書くことや投稿することが目標になってしまうことです。毎日欠かさず投稿している企業でも、「なぜその発信をするのか」という本来の目的を見失ってしまうケースが少なくありません。
発信活動の本当の目的は、売上向上や問い合わせ増加、顧客との信頼関係構築にあります。しかし、更新頻度や投稿数ばかりに注目していると、読者にとって価値のない内容でも「とりあえず投稿しよう」という発想になってしまいます。
- 毎日欠かさず投稿が最優先
- とりあえず何か発信
- 更新頻度ばかりに注目
- 読者価値を考えない
成果なし
労力の無駄
- 発信に明確な意図
- 読者の行動を想定
- 価値ある情報を優先
- 戦略的に情報発信
信頼構築
目標達成
成果を上げる企業は、一つひとつの発信に明確な意図を持っています。「この記事を読んだ人にどのような行動を取ってもらいたいか」を常に考えながら、戦略的に情報を発信しているのです。
成功企業が必ず実践している顧客目線での情報提供
成功している企業に共通しているのは、常に顧客の立場に立って情報を提供していることです。自分たちが伝えたいことではなく、お客様が知りたいことを発信することを最優先に考えています。
具体的には、顧客が日常的に抱えている課題や悩みを深く理解し、それらを解決するために役立つ情報を提供します。商品の宣伝をするのではなく、まずは読者の困りごとを解決することに集中するのです。
この方法により、読者は「この会社は私たちのことを理解してくれている」と感じ、自然と信頼を寄せるようになります。そして信頼関係が築かれた結果として、商品やサービスへの関心も高まっていくのです。顧客目線で考えるコツは、まず自社の商品を一度忘れて、純粋に読者の役に立つ情報は何かを考えることから始まります。
予算・人員に制約がある企業の成功事例|月10万円以下で始める実践方法
予算や人員の制約がある企業でも、適切な戦略と継続的な取り組みで成果を上げることができます。ここでは、月10万円以下で始められる実践方法と、実際に成功した企業の具体的な事例を紹介します。等身大の成功例を通じて、あなたの企業でも実現可能な発信活動の方法を学んでいきましょう。
1人のマーケティング担当者が年間200件の問い合わせを獲得した方法
限られた人員でも大きな成果を上げることは可能です。実際に、1人で担当して年間200件の問い合わせを獲得した企業の取り組みをご紹介します。
株式会社ハッシンラボのクライアントであるA社では、従業員1名のマーケティング担当者が月8万円の予算で運営を開始しました。週2回のブログ更新と月1回のホワイトペーパー制作を基本とし、業界の課題解決に特化した情報発信を継続。SEO対策として、検索ボリュームの高いキーワードを狙った記事制作を行い、6ヶ月で主要キーワードでの上位表示を実現しました。
成功の鍵となったのは、完璧を求めず継続することでした。毎回高品質な記事を目指すのではなく、読者にとって有益な情報を定期的に発信することを重視。また、顧客インタビューを積極的に実施し、実際の声を記事に反映させることで、読者の共感を得るコンテンツを作り上げました。
この結果、サイトへの月間アクセス数は3倍に増加し、問い合わせ数も月平均17件を達成。1人でも諦めずに継続的な発信活動を行うことで、企業の認知度向上と売上貢献を実現しています。
外部の協力を上手く活用して成果を出した中小企業の工夫
社内リソースだけでは限界がある場合、外部パートナーとの協力が効果的です。実際に外部協力を活用して成果を出した企業の事例をご紹介します。
従業員25名のB社では、社内にマーケティング専門スタッフがいない状況でコンテンツマーケティングを開始しました。月7万円の予算で、記事制作を外部ライターに、動画編集を制作会社に依頼。社内では企画立案と品質チェックに集中することで、効率的な運営体制を構築しました。
外部パートナー選びでは、業界知識の有無と継続的な協力の意向を重視しました。単発の依頼ではなく、長期的なパートナーシップを前提とした契約により、コストを抑えながら質の高いコンテンツ制作を実現。また、社内の技術者と外部ライターの定期的な打ち合わせを設定し、専門知識の共有を図りました。
この体制により、月4本の記事と隔月での動画制作を継続。1年後には業界専門メディアからの取材依頼も受けるようになり、認知度が大幅に向上しました。費用対効果も高く、問い合わせ1件あたりのコストは従来の3分の1に削減されています。
効率的な発信活動を実現するためのタスク分担を、以下の表で確認してみましょう。
| タスク | 社内担当 | 外部パートナー |
|---|---|---|
| 企画立案 | 社内 | ― |
| 記事執筆 | ― | 外部ライター |
| 動画編集 | ― | 制作会社 |
| 品質チェック | 社内 | ― |
| 公開作業 | 社内 | ― |
限られた時間で効率的に発信を続ける仕組み作り
忙しい日常業務の中でも継続的な発信を行うには、効率化の仕組みが欠かせません。実際に時間制約を克服した企業の工夫をご紹介します。
C社では、社長を含む3名で発信活動を分担し、それぞれが月1回の記事投稿を担当する体制を構築しました。記事のテンプレートを作成し、構成パターンを統一することで、執筆時間を大幅に短縮。また、日常業務で得た気づきやお客様との会話をメモする習慣を徹底し、ネタ切れを防ぐ仕組みを作りました。
時間の確保方法として、朝の30分間を「発信タイム」として固定化。毎朝この時間を使って記事の執筆や企画立案を行うことで、業務に追われることなく継続的な発信を実現しています。さらに、月末に翌月のコンテンツ企画を決める定例会議を設け、計画的な運営を心がけました。
この取り組みにより、12ヶ月間で一度も更新が途切れることなく発信を継続。完璧な記事を目指すのではなく、読者にとって価値のある情報を定期的に提供することで、フォロワー数は3倍に増加し、問い合わせも月5件から15件に向上しました。
課題別の成功事例と具体的な成果|自社の状況に合わせた選び方
ここでは、企業が抱える代表的な課題(認知度向上、問い合わせ増加、既存客強化)ごとに成功事例を整理してご紹介いたします。読者が自社の状況に近い事例を選べるよう、課題の特定方法についてもガイダンスを提供します。
数値的な改善よりも、実際にどのような変化を感じられるかという視点で、分かりやすく成果をお伝えします。これらの事例を参考にして、自社に最適な発信方法を見つけていただければと思います。
認知度を高めたい企業の発信事例|半年でウェブサイト訪問者3倍
認知度向上に成功した企業では、業界の専門情報を分かりやすく発信することで大きな成果を上げています。
ある中小IT企業では、技術者が週2回のペースでブログ記事を執筆し、業界の最新動向や技術解説を丁寧に行いました。難しい専門用語も初心者が理解できるよう工夫し、図解や実例を多用して説明。この継続的な情報発信により、半年間でウェブサイトの訪問者数が3倍に増加しました。
重要なのは完璧な記事を目指すのではなく、読者にとって価値のある情報を継続的に提供することです。技術的な内容でも身近な例を使って説明することで、多くの人に読まれるコンテンツになります。
問い合わせを増やしたい企業の事例|月5件から50件への改善手法
問い合わせ件数を大幅に増加させた企業では、お客様の疑問や不安を解消する情報発信に重点を置いています。
製造業のある企業では、お客様からよく寄せられる質問をブログ記事として回答し、製品の使い方や選び方を詳しく解説しました。また、問い合わせフォームを見やすい場所に配置し、電話番号も大きく表示。「お気軽にご相談ください」というメッセージも加えて、連絡しやすい雰囲気を作りました。
次の図解で、問い合わせ増加のための具体的な改善ポイントを確認しましょう。
この取り組みにより、月5件だった問い合わせが3ヶ月後には50件まで増加。地道な情報発信と問い合わせしやすい環境作りの相乗効果で、10倍という大きな改善を実現しました。
既存客との関係強化事例|継続的なコミュニケーションで顧客ロイヤリティ向上
既存のお客様との関係を深めて売上向上を実現した企業では、継続的なコミュニケーションに力を入れています。
クラシコムが運営する「北欧、暮らしの道具店」では、商品の新しい使い方や季節に応じた活用法を継続的に発信し、顧客との深い関係性を築いています。Instagramのフォロワーは142万人を超え(2025年3月時点)、単なる商品紹介ではなく「ライフカルチャー」という世界観を通じて顧客エンゲージメントを高めています。この継続的なコミュニケーションにより、リピーターの獲得と売上向上を実現しています。
以下の比較表で、新規獲得と既存客強化のアプローチの違いを確認してみましょう。
| 比較項目 | 新規顧客獲得 | 既存客強化 |
|---|---|---|
| コスト |
5倍のコストが必要 (1:5の法則) |
1/5のコストで実現 効率的な投資 |
| 時間 |
長期的な取り組みが必要 信頼構築に時間がかかる |
短期間で成果が出やすい すでに信頼関係がある |
| 成果確度 |
成約率が低い 平均1〜3%程度 |
成約率が高い 20〜30%も可能 |
| 関係継続 |
ゼロから関係構築 認知・興味から始める |
関係を深化・発展 ロイヤリティ向上 |
| 営業効率 |
リソースを多く消費 人員・時間・広告費 |
少ないリソースで可能 既存チャネルの活用 |
この継続的なコミュニケーションの成功要因は、お客様の生活をより豊かにする情報提供に徹したことです。新規顧客獲得よりもコストが抑えられ、効率的な成長を実現しています。
よくある失敗パターンと回避方法
多くの企業がコンテンツマーケティングに挑戦していますが、期待した成果を得られずに悩んでいるケースが後を絶ちません。ここでは、実際の支援経験から見えてきた失敗パターンを具体的にご紹介し、同じ失敗を避けるための効果的な回避方法をお伝えします。
これらの失敗例を知ることで、あなたの会社では最初から正しい方向で発信活動を進めることができます。失敗を責めるのではなく、改善のきっかけとして前向きに活用していただければと思います。
最初に決めるべき3つのポイントを曖昧にした失敗例
発信活動を始める前に明確にしておくべき重要なポイントが曖昧なまま始めてしまう企業は非常に多いです。特に「目的」「ターゲット」「手法」の3つが不明確だと、どのような問題が起きるのでしょうか。
ある中小企業では「とりあえずSNSで発信しよう」という曖昧な目的で始めました。何を達成したいかが不明確なため、投稿内容もバラバラになり、誰に向けて発信しているかも分からない状態が続きました。結果として、3ヶ月経ってもフォロワーは増えず、問い合わせにもつながりませんでした。
また別の企業では、ターゲットを「経営者全般」という広い設定にしてしまい、刺さる内容を作ることができませんでした。年齢も業界も規模も異なる経営者に向けて発信した結果、誰の心にも響かない当たり障りのない内容になってしまったのです。
このような失敗を避けるには、発信を始める前に必ず3つのポイントを明確にしましょう。目的は「認知度向上」「リード獲得」「顧客育成」など具体的に設定し、ターゲットは年齢・職種・課題まで詳しく決めることが重要です。
コンテンツマーケティングを成功させるためには、最初の設計が何よりも重要です。以下のプロセス図を参考に、段階的に準備を進めてください。
- 認知度向上
- リード獲得
- 顧客育成
- ブランディング強化
- 年齢層・性別
- 職種・役職
- 抱えている課題
- 興味・関心事
- ブログ・オウンドメディア
- SNS(X、Instagram等)
- メールマガジン
- 動画コンテンツ
継続できずに途中で止めてしまう企業の共通点
発信活動を始めたものの、途中で挫折してしまう企業には共通する特徴があります。これらの要因を理解することで、継続可能な仕組み作りのヒントが見えてきます。
最も多い原因は「完璧主義になりすぎること」です。高品質なコンテンツを作ろうとするあまり、1つの記事に何時間もかけてしまい、更新頻度が下がってしまいます。また、短期間での成果を求めすぎて、1ヶ月で成果が出ないと諦めてしまうケースも頻繁に見られます。
体制面での問題も深刻です。担当者一人に全ての作業を任せてしまい、その人が忙しくなると更新が止まってしまいます。さらに、日常業務との両立が困難になり、発信活動が後回しになってしまう企業も少なくありません。
継続するためには、まず60点のコンテンツでも定期的に発信することから始めましょう。完璧を求めず、読者にとって少しでも価値のある情報を提供することを心がけてください。
また、複数人で役割分担をして、一人に負担が集中しない仕組みを作ることが大切です。月1回でも確実に続けられるスケジュールを設定し、長期的な視点で取り組む姿勢を持ちましょう。実際の調査によると、成果を実感し始める時期は「3ヶ月以上6ヶ月未満」が最も多く、焦らず継続することが成功への近道です。
効果測定を怠り改善できない企業が見落とすこと
発信活動の効果を測定せず、改善のきっかけを逃してしまう企業の問題は想像以上に深刻です。実際に、株式会社グルーバーの調査では「効果を図る指標がない」と回答した企業が55.8%に上っており、効果測定の困難さが多くの企業の課題となっています。
多くの企業は「とりあえず発信している」状態で満足してしまい、実際にどのような効果が出ているかを確認していません。アクセス数やいいね数などの表面的な数字は見ていても、最も重要な「問い合わせ数」や「売上への影響」まで追跡できていないケースが大半です。
効果測定を怠ると、どのコンテンツが読者に響いているか、どの手法が効果的かが分からないまま時間だけが過ぎていきます。結果として、効果の低い方法を続けてしまい、貴重な時間とリソースを無駄にしてしまうのです。
改善のサイクルを作るには、まず基本的な指標から確認を始めましょう。Webサイトのアクセス数、記事の滞在時間、問い合わせフォームの利用数など、簡単に取得できるデータから始めてください。
完璧な測定システムを作る必要はありません。月1回でも定期的に数字を確認し、「今月は○○の記事がよく読まれた」「問い合わせが△件増えた」という程度の確認で十分です。重要なのは継続的にチェックする習慣を作り、うまくいかない部分を少しずつ改善していくことです。
成功に導く5つの基本ルール|明日から実践できる具体的な手順
ここでは、数多くの企業の事例分析から導き出された、発信活動を成功に導くための基本ルールを5つにまとめてご紹介します。理論的な説明よりも、読者が明日からでも実践できる具体的な手順として整理しているため、自社の状況に合わせて活用していただけます。
これらのルールを実践することで、限られた予算や人員でも効果的なコンテンツマーケティングを実現し、長期的な成果につなげることが可能になります。
自社の強みと顧客の悩みをつなげる発信テーマの決め方
効果的な発信を行うために最も重要なのが、発信テーマの決め方です。自社が得意なことと、お客様が困っていることの接点を見つけることで、読者にとって価値のあるコンテンツを作ることができます。
まず、自社の強みを具体的に書き出してみましょう。技術力、サービス品質、業界経験など、他社との違いを明確にします。次に、お客様からよく受ける質問や相談内容を整理し、どのような課題を抱えているかを把握してください。
この2つの要素が重なる部分が、あなたの会社が発信すべきテーマとなります。例えば、ITサポート企業であれば「技術的専門知識」と「中小企業のIT課題」の接点である「分かりやすいIT活用方法」がテーマになるでしょう。読者の悩み解決を優先しながら、自然に自社の強みを伝えることが、信頼される発信活動の基本です。
月1回から始めて徐々に増やす無理のない発信計画
継続可能な発信活動のためには、最初から頑張りすぎないことが重要です。月1回という無理のないペースから始めて、慣れてきたら徐々に頻度を上げる方法をおすすめします。
具体的には、まず月1回の記事投稿を3ヶ月間継続してみてください。この期間で、コンテンツ制作の流れや必要な時間を把握できます。慣れてきたら月2回、さらに週1回と段階的に増やしていきましょう。
発信計画を立てる際は、誰が担当するか、いつまでに完成させるかを明確にすることが大切です。また、ネタ切れを防ぐために、お客様からの質問や業界のトレンドをメモしておく習慣をつけましょう。無理のないスケジュールで継続することで、読者との信頼関係を築き、長期的な成果を得ることができます。
継続のコツとして、完璧を求めすぎないことも重要です。60点のコンテンツでも定期的に発信する方が、100点のコンテンツを不定期に出すよりも効果的といえます。
- コンテンツ制作の流れを把握する
- 必要な作業時間を測定する
- 無理のないペースで習慣化する
- 制作プロセスを効率化する
- ネタ帳の作成を始める
- 読者の反応を分析する
- コンテンツカレンダーを活用する
- お客様の質問をコンテンツ化する
- チーム体制を検討する
- 安定した発信リズムを確立する
- 業界トレンドを積極的に取り入れる
- 長期的な成果を評価する
無理のないスケジュールで継続し、読者との信頼関係を築いていきましょう。
小さな成果を積み重ねて大きな効果につなげる改善方法
一度に大きな成果を求めるのではなく、小さな改善を積み重ねていく考え方が、コンテンツマーケティング成功の鍵です。毎回の発信で少しずつ改善していくことで、確実に効果を高めることができます。
注目すべき改善ポイントは、アクセス数、滞在時間、問い合わせ数の3つです。アクセス数が少ない場合は、タイトルやSEO対策を見直してみましょう。滞在時間が短い場合は、内容の分かりやすさや構成を改善します。問い合わせにつながらない場合は、読者が次に取るべき行動を明確に示すことが効果的です。
小さな変化も記録し、何が効果的だったかを振り返ることで、自社に最適な発信方法が見えてきます。月に一度は数値を確認し、前月との変化を分析してください。改善は一歩ずつでも、継続することで必ず大きな効果を生み出します。諦めずに続けることが、成功への最短距離なのです。
今すぐ始められる3つのアクション|自社の発信活動を成功に導く第一歩
発信活動を始めたいと思っても「何から手をつければいいかわからない」「効果的な方法がわからない」という悩みを抱える企業は少なくありません。ここでは、限られたリソースでも確実に成果につなげるための3つのアクションをご紹介します。
これらのアクションは、どれも明日から実践できる具体的な内容です。小さな一歩から始めて、継続的な成果を生み出す発信活動の基盤を作っていきましょう。読者の皆様が実際に行動に移せるよう、段階的に取り組める内容として整理しています。
現在の発信活動を見直すためのチェックポイント
既に何らかの発信を行っている企業にとって、現状を客観的に確認することが改善の第一歩となります。
まず確認すべきは「目的の明確さ」です。認知度向上、リード獲得、顧客育成のうち、どれを最優先にしているかを振り返ってみてください。目的が曖昧だと、コンテンツの方向性がぶれてしまい、効果的な発信ができません。
次に「ターゲットとの適合性」を確認しましょう。想定している読者層に対して、実際に価値のある情報を提供できているでしょうか。アクセス解析データや問い合わせ内容を分析し、狙ったターゲットにリーチできているかを検証することが大切です。
最後に「継続性の確保」について見直してください。更新が止まっている、品質が安定しないといった課題がある場合は、社内体制や制作プロセスの見直しが必要です。
限られた予算で最も効果的な取り組みを選ぶ判断基準
予算制約がある中で、どの発信手法を選ぶかは重要な判断となります。効果的な選択をするための基準をお伝えします。
最も重要な判断基準は「自社リソースとの適合性」です。動画制作が効果的でも、撮影や編集のスキルがなければ継続は困難です。現在の人員のスキルや利用可能な時間を考慮し、無理なく続けられる手法を選びましょう。
次の画像は、各コンテンツ手法の特徴を比較したものです。予算や効果の関係性を把握することで、自社に最適な選択ができるようになります。
- 必要予算:初期投資と月額運用費を総合的に評価(1:低コスト ~ 5:高コスト)
- 制作時間:1つのコンテンツを作成するのに必要な時間(1:短時間 ~ 5:長時間)
- 期待効果:認知拡大やコンバージョンへの貢献度(1:低い ~ 5:高い)
- 継続難易度:定期的な更新や品質維持の難しさ(1:簡単 ~ 5:難しい)
「ターゲットとの親和性」も重要な判断基準です。BtoB企業であればホワイトペーパーやメールマガジン、BtoC企業であればSNSや動画コンテンツが効果的な場合が多いです。ターゲット層がよく利用するメディアや求める情報形式を考慮して選択してください。
継続的な成果を生み出すための社内体制の整え方
発信活動を一時的な取り組みで終わらせず、継続的に成果を生み出すための体制作りが成功の鍵となります。
まず「役割分担の明確化」から始めましょう。コンテンツ企画、制作、公開、効果測定など、各工程の担当者を決めることで責任の所在が明確になります。一人に全てを任せるのではなく、複数人で分担することで負担を軽減できます。
次に示すフローは、効果的な社内体制の構築方法を表しています。各部署の連携方法も含めて参考にしてください。
【画像挿入 種類: 組織図 内容: 発信活動における理想的な社内体制(企画→制作→公開→分析の各工程と担当部署・役割を矢印でつないだ組織フロー図) 目的: 社内での役割分担と連携方法を視覚化し、効率的な体制構築の参考とする 】
- 戦略立案
- ペルソナ設計
- コンテンツ企画
- スケジュール管理
- コンテンツ制作
- デザイン作成
- 編集・校正
- 品質管理
- 配信管理
- SNS運用
- メディア連携
- タイミング調整
- 効果測定
- データ分析
- レポート作成
- 改善提案
市場フィードバック
技術サポート
※ 経営層の理解と協力のもと、各工程の責任者を明確にすることで、効率的な体制運営が可能になります。
「スケジュール管理の仕組み化」も重要です。月次の企画会議、週次の進捗確認など、定期的なミーティングを設定し、計画的に進められる環境を作りましょう。また、経営層の理解と協力を得ることで、継続的な取り組みが可能になります。
社内提案の際は、発信活動が売上や問い合わせにどのような効果をもたらすかを具体的な数値で示すことがポイントです。
コンテンツマーケティングの成果を実現します
まとめ
本記事をお読みいただき、ありがとうございました。限られた予算や人員でも効果的なコンテンツマーケティングは十分に実現可能であることを、具体的な事例を通じてお伝えできたのではないでしょうか。成功の鍵は豊富なリソースではなく、適切な戦略と継続的な取り組みにあることを改めてご紹介いたします。
この記事でお伝えした重要なポイントを以下にまとめました:
- 顧客目線での情報提供を最優先に考え、自社の商品やサービスと関連性の高いテーマで継続的に発信する
- 月1回から始める無理のないスケジュールで完璧を求めず、60点のコンテンツでも定期的に発信することを重視する
- 効果測定を怠らず小さな改善を積み重ね、アクセス数・滞在時間・問い合わせ数の変化を定期的に確認する
コンテンツマーケティングは一朝一夕で成果が出るものではありませんが、正しい方向性で継続的に取り組むことで必ず成果につながります。今回ご紹介した事例や手法を参考に、まずは自社でできる小さな一歩から始めてみてください。読者の皆様が実際に行動に移し、発信活動を通じて企業の成長を実現されることを心より願っております。失敗を恐れず、学びながら改善を重ねていくことで、必ず自社に最適なコンテンツマーケティングの形を見つけることができるでしょう。