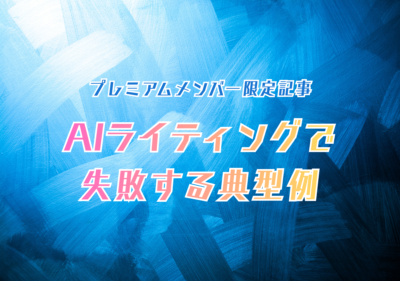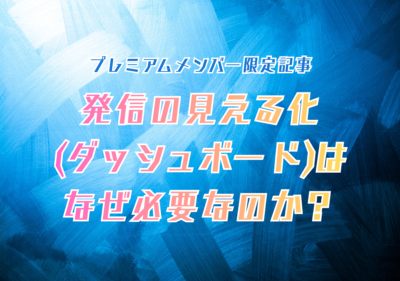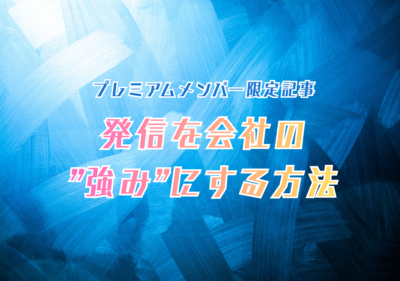「画像のSEO対策って、どこから手をつければいいんだろう…」そんな悩みを抱えていませんか?
Webサイトに掲載する画像には、alt属性(代替テキスト)という設定があります。検索エンジンは画像そのものを「見る」ことができないため、このテキスト情報を頼りに画像の内容を理解しているのです。
本記事では、alt属性の基本的な役割からSEOへの影響、そして実務で使える効果的な設定方法まで詳しく解説します。全ての画像に一律対応するのではなく、限られた時間の中で成果を出すための優先順位付けや、継続的に改善していく仕組み作りもご紹介します。
適切なalt属性の設定は、検索エンジンからの評価向上だけでなく、ユーザビリティの改善にもつながります。「蓄積型発信とは何か?|続けることで成果を出す本質的な発信方法を徹底解説」の視点で、長期的な情報資産価値を高めていきましょう。
alt属性の役割とSEOへの影響を正しく理解する
Webサイトに画像を使う際、見落とされがちながら重要な設定があります。それがalt属性です。
この属性が検索エンジンやユーザーにとってどんな意味を持つのか。そしてSEO効果を正しく理解するためのポイントは何か。実務での優先度を判断する手がかりとして、基本的な役割から確認していきましょう。
alt属性が画像に必要な3つの理由
alt属性は、画像の内容を文字で説明する仕組みのことです。HTMLのimgタグ内に記述され、画像が表示されない時やスクリーンリーダーで閲覧される際に、その内容を伝える役割を果たします。
この設定が必要な理由は、大きく3つ。
まず、検索エンジンが画像の内容を理解するため。Googleなどの検索エンジンは、AI技術で画像内容を一定程度認識できますが、alt属性のテキスト情報と組み合わせることで、より正確に画像を理解しています。
次に、画像が表示されない時にユーザーに内容を伝えるため。通信環境が不安定な場合や、ブラウザの設定によって画像が読み込まれない状況でも、alt属性があれば代わりのテキストが表示されます。ユーザーは画像の情報を失わずに済むのです。
そして3つ目が、視覚に障害のある方が音声読み上げで内容を理解するため。スクリーンリーダーと呼ばれる支援ツールは、alt属性のテキストを音声で読み上げます。適切な説明があることで、画像の情報がすべてのユーザーに届くようになります。
SEO効果は「間接的」である本当の意味
alt属性を設定しても、検索順位が直ちに上がるわけではありません。この点は正直にお伝えしておく必要があります。
多くの方が期待する「設定すれば順位が上がる」という直接的な効果は、残念ながら限定的なのです。
では、なぜalt属性がSEOで重視されるのでしょうか。
それは、間接的な形で効果が現れるためです。適切なalt属性により、Googleの画像検索での表示機会が増えます。ページ全体のコンテンツ内容を検索エンジンがより正確に理解し、そのページが何について書かれているかの評価につながります。
さらに、ユーザビリティやアクセシビリティが向上することで、サイト全体の品質評価が高まる可能性もあります。こうした複数の要素が積み重なり、長期的にはサイトの評価向上につながっていくのです。
蓄積型発信の視点で捉えると、alt属性の設定は一度行えば継続的に価値を生み出します。短期的な順位変動を期待するのではなく、サイト全体の品質を底上げする基盤作りとして取り組むのがおすすめです。SEO対策の本質的な考え方については「SEOはオワコンなのか?AI時代でも企業の発信が必要な理由を解説」で詳しく解説しています。
title属性との違いと使い分け方
alt属性とよく混同されるのが、title属性です。どちらも画像に関連するテキスト情報ですが、役割は大きく異なります。
alt属性は「画像の代替テキスト」。画像が表示されない時に代わりに表示され、スクリーンリーダーで読み上げられます。
一方、title属性は「補足情報」を提供するもの。マウスカーソルを画像に合わせると表示される吹き出しのテキストがこれに当たります。
実際の画面での見え方を想像してみましょう。画像が正常に表示されている場合、alt属性のテキストは通常見えません。しかし、画像の読み込みに失敗した時や音声読み上げの際に機能します。対してtitle属性は、マウスを乗せた時だけ表示される追加説明です。
どちらを優先すべきかと言えば、間違いなくalt属性。SEOやアクセシビリティの観点では、alt属性の方がはるかに重視されています。限られた時間の中で対応するなら、まずはalt属性の適切な設定に注力してください。title属性は、必要に応じて補足的に使う程度で構いません。
| 比較項目 | alt属性 | title属性 |
|---|---|---|
| 表示タイミング | 画像が表示されない時、音声読み上げ時に表示される | マウスカーソルを画像に合わせた時に吹き出しで表示される |
| 主な用途 | 画像の代替テキストとして機能し、アクセシビリティを向上させる | 画像の補足情報を提供する |
| SEOへの影響 | 高い 検索エンジンが画像内容を理解し、画像検索での上位表示に影響 |
低い SEO効果はほとんどなく、検索順位への影響は限定的 |
| 優先度 | 高い(必須) 装飾画像以外は必ず設定すべき |
低い(任意) 必要に応じて補足的に使用 |
効果的なalt属性の書き方と判断基準
ここからは実践的な内容に入ります。
alt属性を設定する際、「全ての画像に同じように対応すればいい」と考えていませんか?実は、画像の種類や重要度によって、適切な対応方法は変わってきます。
効果的なalt属性の書き方を理解することで、限られた時間の中でも成果を出せるようになります。これから具体的な記述例や優先順位の考え方を見ていきましょう。
良い記述例と悪い記述例の具体的な比較
alt属性の記述で最も大切なのは、画像の内容を正確に、かつ簡潔に伝えること。
例えば、商品画像の場合、単に「商品」と書くのではなく「白いセラミック製のマグカップを持つ手」のように具体的な情報を含めましょう。
一方で、避けるべき記述もあります。「SEO対策 コンサルティング 施策 ツール マーケティング」のようにキーワードを詰め込んだ不自然な記述は、検索エンジンからスパムと判断される可能性があります。
ユーザーが画像を見たときに得られる情報を、自然な文章で説明すること。これを心がけてください。
| 画像の種類 | 良い記述例 | 悪い記述例 |
|---|---|---|
| 商品画像 |
推奨
alt=”白いセラミック製のマグカップを持つ手”
画像の内容を具体的かつ簡潔に説明しています。素材や色、動作が明確です。
|
非推奨
alt=”商品”
抽象的すぎて何の商品か分かりません。ユーザーにとって有用な情報がありません。
|
| 人物写真 |
推奨
alt=”笑顔でプレゼンテーションをする女性ビジネスパーソン”
写真の状況、人物の様子、行動を自然な文章で表現しています。
|
非推奨
alt=”女性 ビジネス プレゼン 会議 オフィス 仕事”
キーワードの羅列で不自然です。検索エンジンからスパムと判断される可能性があります。
|
| グラフ・図表 |
推奨
alt=”2024年度の月別売上推移を示す棒グラフ。6月が最高値”
グラフの種類、データの内容、重要なポイントを含めた説明です。
|
非推奨
alt=”SEO対策 コンサルティング 施策 ツール マーケティング”
グラフの内容と無関係なSEOキーワードの詰め込みです。ユーザー体験を損ないます。
|
どの画像から優先的に設定すべきか
全ての画像を完璧に対応しようとすると、作業が膨大になり手が止まってしまいます。
まずは、検索流入が多いページや、コンバージョンにつながる重要なページの画像から着手しましょう。
具体的には、トップページや主要なサービス紹介ページ、よく読まれている記事コンテンツが該当します。Google Analyticsなどの分析ツールでページビューの多いページを把握し、そこから順番に対応していく方法が現実的です。効果測定の具体的な方法については「発信活動の効果測定と改善の回し方|中小企業が成果を数字で把握する方法」で詳しく解説しています。
段階的に改善していくことで、限られた時間でも着実に成果を積み重ねられます。
装飾画像やリンク画像での正しい対応方法
画像の役割によって、alt属性の対応方法は変わります。
デザイン目的の区切り線やアイコンなど、情報を伝えない装飾画像には空のalt属性(alt=””)を設定してください。ここで重要なのは、alt属性自体は記述した上で値を空にするという点です。
これにより、音声読み上げツールが不要な読み上げをせず、重要な情報だけを伝えられます。
一方、リンク画像の場合は必ずalt属性が必要です。リンク先の内容が分かるように「お問い合わせフォームへ」「サービス詳細ページ」のように説明しましょう。
画像がボタンやナビゲーションの役割を果たしている場合、ユーザーがクリックした際にどこへ移動するかを明確に伝えることが大切です。
キーワードの自然な含め方と注意点
SEOを意識してキーワードを含めたい気持ちは理解できますが、あくまで画像の内容を正確に伝えることを最優先にしてください。
自然な文章の中にキーワードが含まれる分には問題ありません。しかし、無理な詰め込みは避けましょう。
例えば「デジタルマーケティング セミナーの様子」という記述は自然です。しかし、「デジタルマーケティング コンサルティング 支援 制作 SEO対策」のような羅列は不自然。このようなキーワードの詰め込みは、検索エンジンからスパムと判断され、ペナルティの対象となる可能性があります。
検索エンジンではなくユーザーのために書くという基本姿勢が、結果的にSEOにもつながります。
画像が記事内でどんな役割を果たしているかを考え、その文脈に合った説明を心がけましょう。
設定後の確認方法と継続的な改善の仕組み
ここからは、alt属性を設定した後の運用についてご紹介します。
一度設定して終わりにせず、定期的に確認しながら改善を続けることで、企業の情報資産として長期的な価値を高めていけます。
検索エンジンは画像認識技術を持っていますが、alt属性は画像の内容を正確に伝えるための重要な情報源として活用されています。適切なalt属性の設定は、サイト全体の品質評価に影響します。
蓄積型発信の考え方に基づいて、継続的にコンテンツの質を向上させる仕組みを作っていきましょう。
無料ツールを使った簡単な確認手順
alt属性が適切に設定されているかを確認する方法は、専門知識がなくても実践できます。
最も手軽なのは、ブラウザに標準で搭載されている開発者ツールを活用する方法です。
Google Chromeをお使いの場合、確認したい画像の上で右クリックして「検証」を選択してください。すると画面の右側や下部にHTMLのソースコードが表示され、imgタグ内にalt属性が記述されているかをチェックできます。
この方法なら、追加のツールをインストールせずに、今すぐ確認作業を始められます。
さらに効率的に確認したい方には、Chrome拡張機能の利用をおすすめします。「Alt & Meta viewer」や「Web Developer」といった無料ツールをGoogleウェブストアからインストールすれば、ページ内の全画像のalt属性を一覧で表示可能です。
複数ページを確認する際には、作業時間を大幅に短縮できるでしょう。
月に一度など、定期的に主要ページの設定状況を確認する習慣をつけると、設定漏れや不適切な記述を早期に発見できます。
次の図解では、Google Chromeを使った具体的な確認手順を示します。画面の操作イメージを確認しながら、実際にご自身のサイトで試してみてください。
新規コンテンツ作成時の設定フロー
今後、新しく記事や画像を追加する際には、作業の流れの中に自然とalt属性の設定を組み込んでおくことが大切です。後から一括で対応しようとすると、手間がかかり漏れも発生しやすくなります。
WordPressなどのCMSをお使いであれば、画像をアップロードする時点で代替テキストの入力欄に説明文を記載しましょう。メディアライブラリに登録する段階で設定しておけば、その画像を記事に挿入する際、自動的にalt属性も反映されます。
このタイミングでの設定を習慣化すると、記事公開後に修正する手間を省けるのです。
コンテンツ制作のチェックリストに「alt属性の確認」という項目を加えておくことも効果的です。記事の最終確認時に、画像のalt属性が適切に設定されているかを必ずチェックする流れを作っておけば、公開前に問題を発見できます。
チーム内で複数の担当者がコンテンツ制作に関わる場合は、ガイドラインを共有しておくとよいでしょう。どのような画像にどんなalt属性を記述するか、具体的な記述例を示しておくことで、担当者による品質のばらつきを防げます。
以下の図では、コンテンツ制作時の各段階でのalt属性設定のチェックポイントを整理しています。制作フローに組み込む際の参考にしてください。
長期的な情報資産として価値を高める考え方
alt属性の設定は、単なるSEO対策のテクニックではありません。
企業が発信する情報全体の品質を高め、すべてのユーザーに正確なコンテンツを届けるための取り組みです。
一時的な検索順位の変動を狙った施策ではなく、継続的に価値を積み重ねる蓄積型発信の一部として位置づけてください。
適切なalt属性が設定された画像は、検索エンジンに正確に理解され、音声読み上げ機能を使うユーザーにも情報が届きます。こうした基本的な配慮の積み重ねが、サイト全体の信頼性向上につながるのです。
また、Googleをはじめとする検索エンジンは、ユーザーにとって有益で使いやすいサイトを評価する傾向を強めています。アクセシビリティやユーザビリティへの配慮は、今後ますます重要になるでしょう。
既存のコンテンツについても、流入の多いページや重要なサービス紹介ページから順次見直していく計画を立ててみてください。
完璧を目指して一気に全ページ対応しようとするよりも、優先順位をつけて段階的に改善を進める方が、実務では現実的です。コンテンツの継続的な改善方法については「中小企業のコンテンツ企画〜制作〜配信の流れ|蓄積型発信で資産を築く実践ロードマップ」で体系的に解説しています。Google Analyticsなどの分析ツールでページごとのパフォーマンスを確認しながら、効果の高いページから着手していきましょう。
長期的な視点で取り組むことで、alt属性の設定は企業の情報資産の質を底上げする基盤となります。今日から始めた小さな改善が、数ヶ月後、数年後のサイト全体の価値につながっていくはずです。
アップロードされたファイルを確認させていただきます。内容を確認しました。記事全体のまとめ文章を作成いたします。
まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。画像のalt属性は、見落とされがちながらもWebサイトの品質を底上げする重要な要素です。本記事では、基本的な役割から実務での効果的な設定方法まで、段階的にご紹介してきました。ここで改めて、押さえておくべき重要なポイントを振り返ってみましょう。
- alt属性は検索エンジンの画像理解、画像非表示時の代替表示、音声読み上げ対応という3つの役割を果たし、SEO効果は直接的ではなく間接的なものである
- 効果的なalt属性は画像の内容を正確かつ簡潔に伝えるものであり、キーワードの詰め込みは避け、優先度の高い重要ページから段階的に設定していく
- ブラウザの開発者ツールやChrome拡張機能で設定状況を定期的に確認し、新規コンテンツ作成時にはalt属性の設定を業務フローに組み込んで継続的に改善していく
alt属性の適切な設定は、一時的なSEO施策ではなく、企業の情報資産としての価値を長期的に高めていく取り組みです。完璧を目指して全てを一度に対応しようとするのではなく、優先度をつけて段階的に改善を進めることが、実務では最も現実的で効果的なアプローチとなります。今日から始める小さな一歩が、数ヶ月後、数年後のサイト全体の品質向上につながっていきます。蓄積型発信の視点で、ユーザーにとって価値ある情報を提供し続けるための基盤作りとして、ぜひ取り組んでみてください。